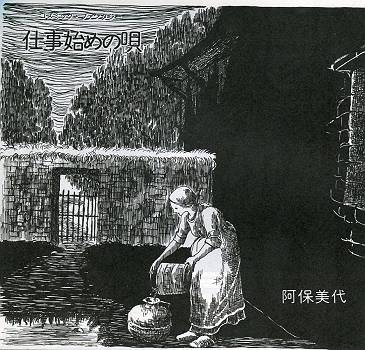|
ちゅっ、中編だぜ! 御代官様!(店主は風邪気味で熱があるため文章が少々酩酊しております)
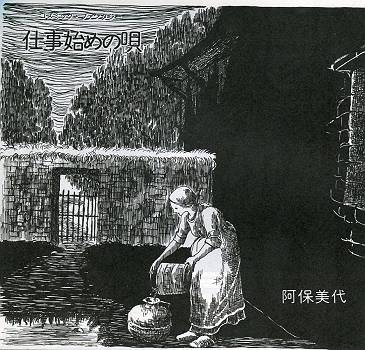
・阿保美代「仕事始めの唄」 初出:平河出版社『ザ・メディテーション』1978年冬季号
阿保美代は1972年のデビュー以来長く講談社『週刊少女フレンド』、『別冊少女フレンド』、『mimi』等を活躍の舞台としていた。
店主は実をいうと講談社系の少女マンガ雑誌を、リアルタイムではほとんど読んでいなかった。しかし全く読まなかったというわけでは無いので、どこかで阿保美代の作品をリアルタイムで読んでいた可能性が無いわけでは無いはずだが、やっぱりどこにもその記憶が無い。
そんなわけで阿保美代の作品を知ったのは、東京三世社の『ルフラン』(1987年5月発行)という単行本だった。少し大人向けのファンタジー作品で、絵柄はとても気に入ったけど、ストーリーとしては抽象的であまり印象に残らなかった。そんな阿呆美代を強烈に意識するようになったのは、平河出版社の『ザ・メディテーション』という神秘主義とか精神世界を扱ういわゆるスピリチュアル系雑誌に掲載された「仕事始めの唄」というわずか5ページの作品(もっとも阿保美代の作品は4ページから多くても10ページがほとんどだが)からだった。
それは秋の終わりに夫を亡くし寡婦となった女が、その喪失感に馴染めないながらも、やがて訪れる春を迎え入れる姿を描いたものだ。ペンで細かく引っ掻くように描かれた陰鬱な空と大地。この作品に強く惹かれた店主は、遡るようにフレンド系で執筆された『お陽さま色の絵本』を初めとする単行本を古書で集めた。そこには、初夏に吹く風のように爽やかで明るい草原と人気のない暗い森に降る雪景色の両方が不思議に同居していた。
黄金色に輝く小麦畑に吹く風を描くことができるマンガ家は数いれど、シュバルツヴァルド(黒い森)に静かに降り積もる雪を描くことができるマンガ家は稀有だと思う。
阿保美代の作品を時系列で追ってみると、その個性的で独特な魅力をもった作品から、やがてだんだんと凡庸な作品になってくるのを感じる。それは恐らく阿保美代が変節したのではなく、阿保美代が描く場所の方が変節してしまったためだと思う。
阿保美代がその才能を発揮できる場所を失ったマンガ界というものは、実にとても大切な物を失ってしまったように思う。

・太刀掛秀子「ひとつの花もきみに」 初出:集英社『りぼんオリジナル』1984年春の号
また大学時代の話になるのだけれど、1970年代後半に実は隠れたようにこっそりと集英社『りぼん』を読んでいた。何を今更と言われるかもしれないが、白泉社『ララ』は大っぴら読めても『りぼん』はやっぱりちょっとすごく恥ずかしかったのだ。羞恥心もまだ完全には捨て切っていなかったしね。
1970年代後半の『りぼん』では、乙女チックまんがとかアイビーまんがとか呼ばれる路線が隆盛を誇っていた、その代表格に陸奥A子、田渕由美子、太刀掛秀子の3人が居た。当時の『りぼん』の読者は、ほぼ間違い無くこの3人のうちの誰かのファンだったといっても過言じゃないと思う。ちなみに店主は太刀掛秀子が好きでした。
太刀掛秀子といえば、代表作は「花ぶらんこゆれて…」で決定だと思う。これは多分誰に意見を聞いても揺るがないと思う。ただ、店主はこの「花ぶらんこゆれて…」が実は苦手だった。この作品に欠点があるとか、これが代表作ではないとか、そういうつもりは毛頭もない。ただ単純に、幼い子供が悲惨な状況にあるという描写が長く続く作品が苦手だというそれだけである。悲惨な状況がごく短かったり、子供といってももう少し年齢がいってればOKなんですが、子供が小学校低学年以下くらいだったり悲惨な状況自体がメインの軸だったりするともうアウトです。どうしても読み続けることができません(涙)
てなわけで店主がお薦めするのは「青いオカリナ」とか「ひとつの花もきみに」とかこのあたり。どちらもすごく悲惨で切なくて悲しいお話。今回どちらに絞るか散々悩んだけれど、結局「ひとつの花もきみに」の方を選択。その差はごく僅かです。
ところで「ひとつの花もきみに」のあらすじを書くのは結構難しい。何故かといえば話が単純すぎるから。試しにちょっと書いてみるとこんな感じ。
2年ぶりに故郷に戻った嗣郎は、大学時代に2年後輩だった柚子の結婚を知らされる。大学の映画サークルで知り合ったふたりはかつて同棲生活を送った仲だった。まだ若すぎるふたりの同棲生活は、ごく単純な気持ちのスレ違いによって僅か1年で破局を迎えたのだった。柚子の結婚の報を聞いても何も気持ちが動かないと話す嗣郎に、友人は柚子が抱えていたある事情を告げる…
店主のあらすじ書く才が無いのも起因しているかもしれないが、こうやって書いてみると自分でもどこが面白いのかさっぱりわからない。昔の昼メロにゴロゴロと転がっているような話である。
ところがこの単純でつまらなそうな話が、太刀掛秀子の手にかかると最上級のマンガに化けてしまう。これは本当にすごい才能だと思う。しかも少し大人向けのこの話が太刀掛秀子の円熟期のシットリした絵と実によくマッチしていた。
太刀掛秀子には90年代になってもこの路線の作品をレディス誌辺りで描き続けて欲しかった。今はもう叶うことない夢だけど…

・狩撫麻礼、中村真理子「days 時の満ちる」 初出:スタジオシップ『コミック劇画村塾』1985年2月号〜86年9月号
原作者は男だけど、作画は女性なんで今回の選択基準にはセーフということで…。
2度の外タレ興行に失敗し3億5千万円の負債を抱えた”呼び屋”馬渡真助。家財道具を売り払い夜逃げを決め込んだその日の晩、まるで記憶にない婚約者を名乗る美女がウェディングドレスを持参で現れる。奇妙でそれでいて甘い逃避行が始まる。
煮詰まっちゃってニッチもサッチも行かなくなった男のもとに、正体不明の女が転がり込むという構図は、大前田リンの「ガケップチ・カッフェ−」を思い出すが、雰囲気的にはまるで違う。まあ、狩撫麻礼が原作なんで基本的にはハードボイルド路線です。
甘々の逃避行も全20話480ページ中の前半7話くらいで、後半は女の正体をめぐるミステリアスでハードボイルドな展開となる。こういった展開は嫌いじゃなないけど、しまいにはペンタゴン(米国国防総省)迄出てくるのは、さすがにちょっと風呂敷広げ過ぎかなぁと思う。
実のところ狩撫麻礼も中村真理子もそれほど好きな作家というわけではない。狩撫麻礼に関しては、たなか亜希夫との共著「迷走王ボーダー」は大好きだったが、所詮その程度。中村真理子に関しては、小学館の『ビッグコミック・フォアレディ』で何か連載やっていたなくらいの認識しかなかった。
不思議な事に大して作者が趣味でもないのに、何故かこの「days 時の満ちる」作品だけをやたらと気に入っている。京都料理の芋棒みたいに素材同士の絶妙なカップリングが醸し出す、”出会いもの”なんじゃないかとも思ったのだが、よく考えたら同じ狩撫麻礼・中村真理子共著の「ギルティ」とか「天使派リョウ」は、まるで興味がわかなかった。ハマるととことんハマりだす店主にとっては実に不思議なことである。
物語のラストは、固茹で卵(ハードボイルド)をさらに男の哀愁で煮付けたようなモノローグで終わる。
”俺は特別な男ではない もっと早く気がつくべきだった―”。
最高に切なくて最高にかっこいいラストである。ただし間違っても自分は、こんな後半生だけは送りたくないけどね。

・「D ディー」洞沢由美子 初出:徳間書店『月刊アニメージュ』1987年10月号〜90年2月号
洞沢由美子に関しては、馬鹿な勘違いをしていた記憶がある。初めて読んだ作品が何だったかに関しては、さっぱり記憶が無いのだけれど、初期に秋田書店『サスペリア』や主婦と生活社『ホラーパーティ』等で読切のホラー作品を描いていたので、てっきりホラー漫画家用のペンネームとして”ほらさわ”を使用しているのだと思い込んでしまった。”洞沢”が本名だということも、元々はアニメ関係の人だということも恥ずかしながら後から知りました。(たしかにTVアニメ「めぞん一刻」3期OPを今観ると、このぶっとい響子さんの太ももは洞沢由美子以外の何物でもないことに納得する)
『月刊アニメージュ』は読んでいなかったので、この作品は単行本で知りました。単行本は最初に徳間書店からアニメージュコミックスワイド判として全3巻で、しばらくしてから主婦と生活社から全2巻版が出ました。ちなみに初期のタイトルは”D
[di:]”という表記でした。
話の内容はSFです。しかも人類絶滅ものです。ある日突然原因不明の伝染病により、人類の大半が死に絶えます。残されたのは何故か病気に体制があった数名の若者たち。若者たちは東京都下で共同生活を始めるが、やがて生き残った自分たちの正体が、”D”と呼ばれた合成人間とその”D”から生まれた子供という2種類であることを知る。しかも”D”は、加齢により精神に変調をきたした後に死亡し、”D”から生まれた子供は生殖能力を持たないことも判明する。
この手の設定のSFであれば、通常は”D”を創ったものは何者かということが後半のテーマになるのだが、実のところそんな話は欠片も出てこない。
人類滅亡テーマのSFといえば、だいたい二つのパターン集約される。ひとつはネビル・シュート「渚にて」の様に、滅亡を迎え入れるパターン。もう一つは小松左京「復活の日」のように、最後に一発大逆転のパターンである。しかしこの「D ディー」という作品はどちらにも属さない。
人類は病気で絶滅し、残された”D”は実は人類ですらなく、やがて発狂して死ぬ運命、”D”から生まれた子供は次代への生殖能力がないという八方塞がりの状態である。普通ならばたとえ片鱗だろうと何らかの解決策を示して終わるのがSFとしてのパターンだと思われるが、そうした要因は一切ない。
しかしだからといって残された彼らが積極的に滅亡を受け入れることも自暴自棄になるということもない。
主人公たちは、たとえ次代への生殖能力を持たない子供であっても、その誕生を喜び受け入れ、そして新しい仲間を探すために海を渡り大陸へと向かう。
およそSF作品というものは大なり小なりの不健全性をを伴うものだ。そもそもSFというもの自体の根っこからして不健全性の塊とも言える。
「D ディー」も設定や状況に関しては、かなりのSF的不健全性が付きまとうが、主人公たちの行動や志向は、限りなく真っ当で健全である。そしてそれが健全であるがゆえにSF的派手さはないが、長く人の記憶に残るSF作品となっているのだと思う。
次回後編に続きます。
|